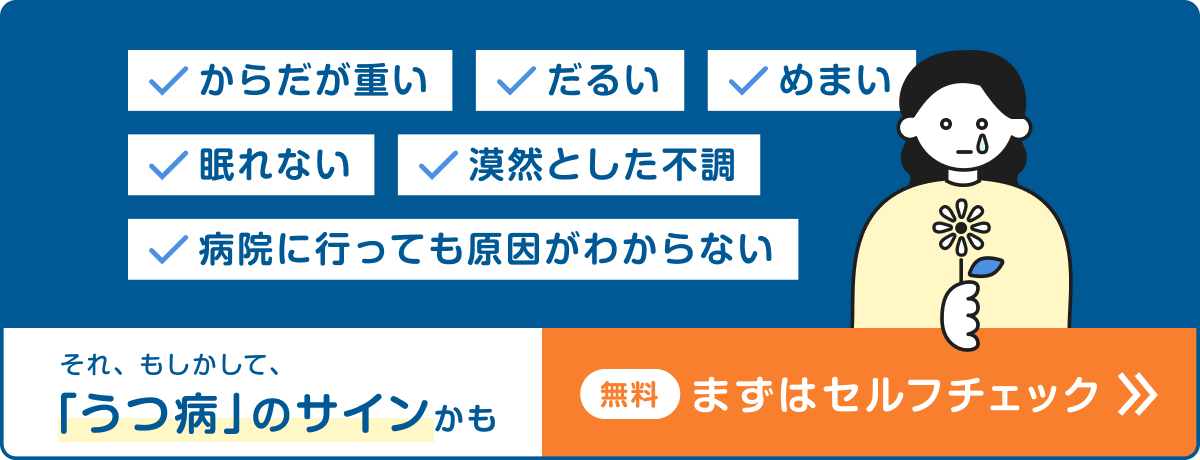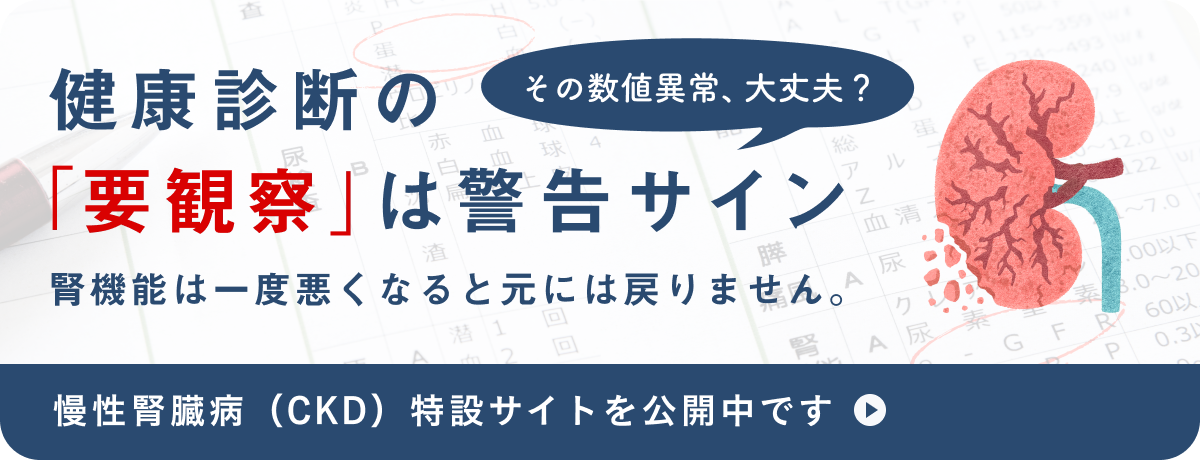「尿勢低下と尿道口違和感」の追加相談
person40代/男性 -
前回に続き再度お世話になります。
前回8/9までの経緯後なのですが、
8/10 8/11 一日中微熱(36.8〜37.3度)
尿勢低下あまり変わりなし
8/11の夕飯後、尿勢や尿道口の違和感が低減して来た感じ。就寝前クラビット2錠、アセトアミノフェン服用。
8/12 4:00 37.8度
薬を追加してもらうために再度今までと違う泌尿器科を受診
・採尿
潜血− 赤血球0.5 白血球0.5 細菌なし
・超音波(膀胱、前立腺、腎臓)
前立腺42ミリ?(肥大?炎症?)
炎症で腫れているのか元々なのか分からない。心配なら10月にもう一度エコー
・直腸診、前立腺が熱いため前立腺に炎症は残っていると判断
・尿勢検査 問題なし
・残尿検査 40ミリリットル
その後一日中横になって過ごす。尿量や尿勢、違和感?はもうほぼ無いと言った感じ。
一日中36.7〜37.3℃
頭痛もあったため昼食後にアセトアミノフェン服用。就寝前にクラビット2錠。
8/13 体は辛くないが何となく火照る感じ。
熱は一日中36.6〜37.3度と言った感じで微熱が続いている。尿の感じは日常に戻り排尿するのに苦労もせず、尿勢も強く、量も水分に合った量出ている感じ。残尿感もなく、尿道口に違和感もなしです。
ただこの続く微熱が何とも気になります。
尿検査で細菌なし。だが炎症はある。と言う事はあるのでしょうか?
またその炎症から微熱が続いているのでしょうか?もう1週間熱が続いており、なんで?と気が滅入りそうです。
細菌居ないのにいつまで微熱?自分は大丈夫なのか?と心配ばかりしてしまいます。
今日でクラビット使用で丸4日(8/9夜から)です。全部で14日分クラビットはいただきました。薬が効けばもっと早く熱は引くと思っていたので心配です。よろしくお願いいたします。
尿勢低下と尿道口違和感
腰痛→尿勢低下→発熱という経緯があり相談させていただきました。
8/5、午後から腰、背中に筋肉痛のような痛みと怠さ
40度近い職場なため熱中症かと思い早退
8/6、前日より軽減
夕食後に背部強張りと体が怠くなって来た
8/7、背部の痛み、強張りは無くなった。
朝方、トイレに行くと明らかな尿勢低下あり。尿道口付近に軽いジワー(熱い?)という感覚(前日就寝前までは普通)
体は楽だが一日中排尿に時間がかかる
(30〜60秒程度)最終的な量は通常
8/8(火)
体調は悪くなくいつも通り。排尿だけ前日と変わらず。
泌尿器科に行き尿検査
→タンパク、潜血マイナス
赤血球 0.1(正常1.0)
白血球 1.6(正常1.0)
軽い炎症を尿路で起こしているという事でナフトピジルを処方される
夕食後に薬を飲み就寝。夜中に2回トイレ。排尿変わらず、尿道口違和感も同じ。
8/9、起床時から腰が痛く、なんとなく怠い。体が熱く体温を計るも36.5度
朝食後ナフトピジル服用
午前中、腰が痛く顔も火照る感じがして体が辛い。夕食体が怠く熱いため検温。38.6度あったため夜間外来で受診。病院到着時は37.6度。
採尿、採血(結果は写真添付しました)
検査内容から今のところ尿路感染としか言えない。という事でクラビットを処方。
5日分処方され泌尿器科でいただいたナフトピジルは服用せずクラビットだけで良いと言われる。
現在は熱もなく背部痛もなく頭痛程度ですが排尿は変わらず。
そこで連休に入ってしまうので今後の事で質問です。
・薬は5日分なのですがどのように行動したら良いですか?
・何の心当たりもないのですが何の病気が考えられるでしょうか?
・前立腺癌のような悪性も考えられるのでしょうか?
心気症なので次から次と心配になってしまいます。よろしくお願いいたします。
person_outline心配ばかりさん
各回答は、回答日時点での情報です。最新の情報は、投稿日が新しいQ&A、もしくは自分で相談することでご確認いただけます。
本サービスは医師による健康相談サービスで、医師による回答は相談内容に応じた医学的助言です。診断・診察などを行うものではありません。 このことを十分認識したうえで自己の責任において、医療機関への受診有無等をご自身でご判断ください。 実際に医療機関を受診する際も、治療方法、薬の内容等、担当の医師によく相談、確認するようにお願いいたします。